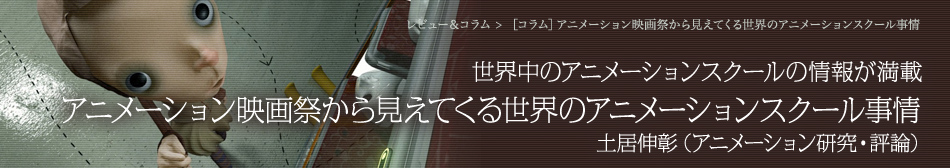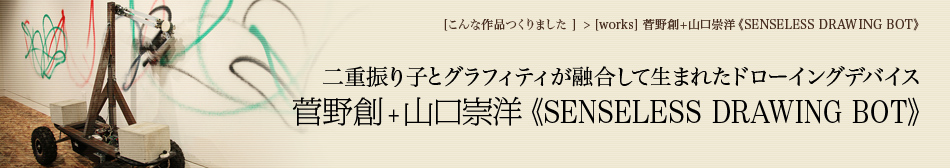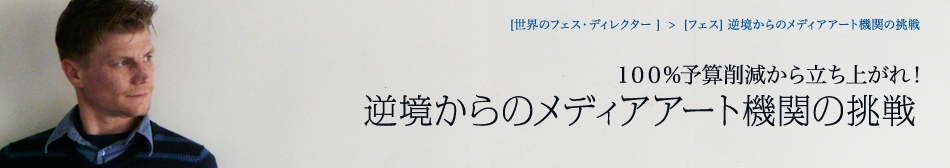[Works] Pendulum Choir(振り子の合唱団)
July 28th, 2011 Published in こんな作品つくりました
作品を身近に感じたり、面白く思える1つのきっかけは、その作者のことや過去の作品を知ることだったりします。「こんな作品つくりました」では、毎回、1つの作品やプロジェクトを取り上げ、興味津々に見てみることで、作家やその背景に迫ります。
第1回目となる今回は、傾く9人の男性が写し出された不思議な写真から始めます。
震災から1ヶ月後の4月中旬、日本の様子を心配するメッセージとともにメールでとどいた新作の画像と動画のwebリンク。送り主は2月に出会ったスイスのアーティスト、アンドレ・デコステール。新作のプロジェクトを切り取った突拍子もない画像の迫力に、なんだか元気をもらったことを思い出します。
振り返って今年2月。六本木・東京ミッドタウンの広い吹き抜けに、たった10日間だけ、出現したオブジェを知っていますか?
はるばるスイスから運ばれてきた総重量780kgの《Cycloïd-E》です。金属のアームが接続部を起点に蛇のようにくねくねと動き、同時に内蔵されたスピーカーからアコースティックな音が発せられ、その音が動きに連動して変化する音響彫刻。この作品は第14回文化庁メディア芸術祭アート部門の大賞に選ばれ、展示されました。作者は、Cod.Actという2人の兄弟ユニットで、メールをくれたアンドレは兄。作曲家として活動する一方で、建築家の弟ミシェルはともに、Cod.Actとして作品を発表し続けています。2月に初来日したときは、初めての東京に戸惑いながらも、興奮しがちに、兄弟そっくりな服装で登場したCod.Act。非常にタイトな展示スケジュー ルの中でも、つねに笑顔を絶やさず周囲に気を配りながら、しっかりとペースを保って的確に作品の展示や調整に取り組んでいたのが印象的でした。彼らの新作が冒頭の《Pendulum Choir(振り子の合唱団)》。
新作の画像では、男性たちが鉄骨の重々しい装置に縛りつけられ、ばらばらな方向に傾いています。写真からでも推測出来るスケールの大きさ。そして、装置にくくりつけられ、真剣な表情で口あける9人の男性。送られてきた画像の不可解さに興味を持ちました。
たくさんの人を巻き込んだ(おそらく)ビックプロジェクトをどのように遂行して、公開出来たのか?そして、そもそもこれはアート作品なのか?否、Cod.Actがアート作品として確信をもって発表出来たのはなぜか?いろいろな疑問が急に頭に渦巻いてきました。
そこで、たっぷりの質問を送ってみることにしました。作品のこと、Cod.Actのこと、活動のこと。そしてこれからのこと。
Q1. 《Pendulum Choir(振り子の合唱団)》の制作期間を教えてください?
リサーチを始めたのは2007年の終わりごろで、ちょうどスイスで開催されるアートとテクノロジーのフェスティバルに招待されていた時期でした。《Pendulum Choir》のコンセプトと、基礎部分の模型を作ると、工業学校が、合唱団の動きをシミュレーションするソフトウェアを制作してくれました。2008年からは、資金を集め始め、作品が公開出来た2011年4月まで制作を続けました。同時期に実現したプロジェクトが《Cycloïd-E》でした。
Q2. 今回の作品では、なぜ人間そのものが、まるで装置の一部のように作品に組み込まれたのでしょうか?そして今回の作品では人間が生み出す生の音源です。その音源へのこだわりという点から、これまでの作品の違いを教えてください。
Cod.Actのプロジェクトでは、「動き」と「サウンド」が必ず結びついています。「動き」と「サウンド」の関係性に対する尽きない探求心と、最良なバランスを見つけ出そうとする努力を証明するのが個々のプロジェクトと言えるでしょう。全てのプロジェクトにおいて、「動き」と「サウンド」を生み出す装置を開発します。大抵、装置は、人(鑑賞者やCod.Act)が操作しますが、そうすることで「動き」と「サウンド」に加えて、「人」と「装置」の関係がプロジェクトに加わります。
《Cycloïd-E》と《Pendulum Choir》の直前に実現したサウンドインスタレーション《ex pharao》 では、鑑賞者がオーケストラの楽曲をワイヤーの操作で指揮することが出来ます。《ex pharao》の完成後も、楽器や合唱による音楽をテーマとして取り上げたいと思いました。そして《Pendulum Choir》は、2つの興味から生まれました。楽器や肉声による音楽をテーマとしたプロジェクトを実現させること、そして「動き」の観念も取り入れた自作の装置とその音楽を関連付けることでした。
《Pendulum Choir》では、肉声による音色・言葉・リズム・強さ・密度と、装置の速さ・位置・加速度を、直接結びつけ連動をさせたいと思いました。制約のある装置の動きと歌い手の位置を、歌声に直接反映させたかったのです。加えて、センサーや情報を操作するような中間的なシステムを使わずに、「動き」と「サウンド」の自然な関係を引き起こしたいと思いました。
肉声で歌う場合、呼吸と息継ぎが重要です。作品のパフォーマンス中、歌い手たちの、呼吸器官の状況が通常とは異なっていることが分かります。とくに歌い出しや歌い上げるタイミングです。歌い手の位置や傾きを装置で動かし、身体的な状況が、歌い手の声に影響する位置に移動しました。歌い手は、これまでのプロジェクトの中では新しい要素です。
《Pendulum Choir》において、歌い手は不可欠な要素であり、音楽を生み出す要素でもあります。装置の一部としての人間の存在は、ストーリーを感じさせるだけでなく、感情に訴える重要な印象を作品全体に持ち込むことになります。結果、形態としての人間と機械の関係を見せると同時に、両者ともが生き生きとした対等な要素であることを示しています。
Q3. この作品は人間が9人も組み込まれる、スケールの大きい作品です。スケールはどのように決定されましたか?なぜ9人なのかということも理由があれば教えてください。
当初、このプロジェクトは50人の歌い手で作り上げたかったのですが、必要とされる油圧式の機械装置の複雑さとその費用から、50人は実現できないことはすぐに明らかになりました。最終的には9名の男性ソリストを選びました。バス、テノール、アルトの歌い手を3名ずつにすることでバランスがとれることと、9人の歌い手と装置の見栄えの良さを確信していました。
私たちはJOC (Jeune Opera Compagnie) に連絡をしました。JOCは、現代音楽を専門とするスイスでは有名な合唱団です。この合唱団は、作曲家であるFrancois Cattin と指揮者のNicolas Farineによって組織され、歌い手はスイスを中心に近隣の国から参加しています。彼らとのコラボレーションを本当にうれしく思いました。
Q4. そして、今回完成した作品の感想を教えてください。
《Pendulum Choir》は、私たちにとって、芸術的にも技術的にも難しい賭けを伴うような大きなプロジェクトでした。また、多くの人々とコラボレーションをするのも今回が初めてでした。このプロジェクト特有の制約を振り返ると、非常に喜ばしい結果だったと思います。また、公共のメディアで紹介されたことも嬉しく思っています。ただ、この経験の後で、作風を戻したくなる可能性もあると感じています。具体的には、機械とサウンドの実験的な関係性よりも、具体的なものに重点を置き、ポエティックではない極端に芸術的なプロジェクトです。
Q5. Cod.Actは、兄弟ユニットですが、ユニット名の由来を教えてください。
《Poe transcripts》という私たちの初めのプロジェクトは、4人のミュージシャンと、コメディアン1人でライブプロジェクションを用いたものでした。当時は、多領域を横断するようなプロジェクトに取り組んでいました。そこで私たちは様々な表現分野にいるアーティストが理解しうるような記号のようなもの、例えばダンス等で使われていますが、芸術の分野で採用されているあらゆる手法を用いて、独自の楽譜のようなものを作ろうとしました。ユニット名のCod.Actは、探求をしているcode (記号)とact (活動、行為)の2つの言葉をまとめたものです。
Q6. 近年では、身体、空間、音、装置、様々な要素がアート作品の要素として組み込まれるようになりました。Cod.Actの作品にはその要素が組み込まれています。プロフィールを拝見すると二人が30歳を過ぎてから、ユニットとして活動を始められています。現代のアートを巡る状況と、活動を始めようと思ったきっかけに何か関連はあるのでしょうか。また、Cod.Actの作品では、音響空間を作ることと装置を作ることが合致されています。お二人が育ってきた環境で、この要素が強く結びついていた原体験はあるのでしょうか?
私たちは30代になってからCod.Actとして一緒に活動を始めました。以前は、それぞれの専門性を尊重して独自に実験に取り組んでいました。一緒に活動する決心をした時にはすでに、作品の方向性と芸術的な表現に関してお互いの領域を侵食するようになっていました。付けくわえなければいけない重要な点として、私たち兄弟は、音楽と建築という異なる専門領域を歩んできました。Cod.Actを立ち上げた時には30代になっていたというわけです。
私たちの機械やテクノロジーに対する嗜好は、確実に幼年期から始まっていて、たくさんの刺激を受けてきました。父親は、電気関係の技術者で、彼は頻繁に電気やコンピューターを使った実験に対して手助けをし、実現させてくれました。彼の実験室は魅了される空間で、多くの機会で使用させてくれました。こうして常に科学と構造への興味を持続してきたので、科学的な現象から頻繁にアイディアが出てきます。そして音響装置に発展させるのが好きなのです。Cod.Actのプロジェクトはこうして誕生していくのです。
Q7. 今回の作品だけではなく、これまでの作品にも一貫して作曲家と建築家という二人の専門性が生かされていると思いますが、兄弟で作品を作る面白さは何ですか。規模の大きい作品を長期的なプロジェクトで進行させて行く上で、意見の相違なども出てくると思いますが・・・・?
私たちの作品は、コンセプチュアルアートよりも応用美術や実用的な工学に結びついていると思います。「知識」に重きを置くことで、プロジェクトとしての「強度」を生み出していると思います。その「知識」は、特定の領域を専門とすることでのみ取得可能なものです。私たちはそれぞれ作曲家と建築家として活動しています。Cod.Actの作品の中では二つの分野が補完的に作用しているのです。
私たちのルールは確立されています。それは、アイディアは、実際の経験から生み出されていて、その逆はないということです。私たちは同じ視点をもってアートに取り組んでいます。それぞれ仕事をしているので、距離をおいて、あまりコミュニケーションを取らないことも多々あります。ある程度時間が経った時に、それぞれが作ったものを組み合わせてみます。ここからCod.Actのプロジェクトが始まります。
Q8. 現代社会では音を聞く環境は実に様々で、いろいろな装置や空間が存在しています。インターネットでパーソナルに音楽を楽しめる一方で、映画館などでも臨場感のある音響体験をすることは可能だと思います。こういった状況下の2010年代において、これからの活動へ向けてCod.Actの意識や感じることがあれば教えてください。
その通りだと思います。デジタル技術が発達し、一般化したことで、音楽を生産し消費することに関して、大きな変化が起こっていると思います。社会と音楽の関係は、急速に変化していて、同時にイメージや情報の在り方もそれ以上に変化しています。そしてそれら全てにすぐさまアクセス出来きます。この飽和状態の中で、個人の表現に関して、その質が評価されないまま分別なく消費される傾向があると思います。
しかしながら、もし、アーティストが、何かを伝えたい、明らかにしたいと思い、発想を共有したい、もしくは守りたいとします。そして、それを確実な方法で実現出来るのであれば、メディアの進化の中にあっても、アーティストは自分を表現する場所を見出すことが出来ると思います。
これからのCod.Actの活動に関しては、いま丁度《Pendulum Choir》を完成したばかりで、次の作品の話をするのは、早すぎるかもしれません。いくつかアイディアを出してアトリエで実験は初めていますが、まだまだ先は分からないですね。
そして、最後に、ダウンロードに時間を要しますが、是非作品動画をご覧ください。
http://www.codact.ch/videos/pendulum/pendulum_video.html
————————————————————————————————————————————–
Cod.Act
André Décosterd と Michel Décosterdによるユニット。パフォーマンスやインタラクティブインスタレーションなどを展開。際の動きが、生み出される音に変換され、音響空間を作り出す独自のデバイスを作り上げ、国内外で発表している。Michel Décosterd:1969年スイス生まれ。造形芸術や建築、サウンドマシンの分野で活躍。André Décosterd:1967年スイス生まれ。音楽家。作曲家。
公式サイト http://www.codact.ch/
————————————————————————————————————————————–
アンドレからの答えに一環していたのは、これまでの二人の専門的な知識と経験に関する自負と、その探究心です。それが直接作品に直結していることが分かりました。ただその探究心を、自己満足で終わらせずに、作品として提示するために、じっくりと腰を据えた長期的な取り組みをしていて、その準備期間を通じてますます作品に対する確信が生まれてくることが伝わってきました。この《Pendulum Choir》は、「ライブ」で味わってみたいです。いつか世界のどこかで。
引き続き、この「こんな作品作りました」では、作品を観ているだけはなかなか知ることが出来ない、沢山のエピソードを直接作者に尋ねながら作品に近づいていきたいと思います。